授業のワンポイント
解の吟味の指導
■解の吟味の指導
方程式を使って問題を解く手順は,次のようになります。
1.問題の中の数量に着目して,数量の関係を見つける。
2.まだわかっていない数量のうち,適当なものを文字で表して,方程式をつくって解く。
3.方程式の解が,問題にあっているかどうかを調べて,答えを書く。
1,2年の方程式の利用題では,方程式の解がそのまま問題の答えとなる場合が多く,どうしても,形式的に解の吟味をしがちです。
ところが,二次方程式の利用では,方程式の解が問題の答えとしてあわない場合が多くでてきます。教科書の二次方程式の利用にある問題のうち3題は,方程式の解のうち1つが問題の答えとしてあわないものを扱っています。このような例を意識的に取り上げ,解の吟味の必要性を感じさせたいものです。
解の吟味を検算ととらえ,計算ミスをしているかどうか,もとの方程式に代入して確かめることと思っている生徒もいます。このような生徒には,二次方程式は一般に解が2つあるので,どちらが答えになるのか問題に戻って考える必要性を感じさせ,また,方程式の解としてはあっていても,利用題の答えとはならない場合があることを理解させるよい機会です。
方程式を使って問題を解くときは,常に選んだxがどのような条件にあてはまる数量であるかを把握することが大切です。
二次方程式の利用題に取り組む際には,xの値が取り得る範囲を確認するよう,毎回生徒に意識させるとよいでしょう。
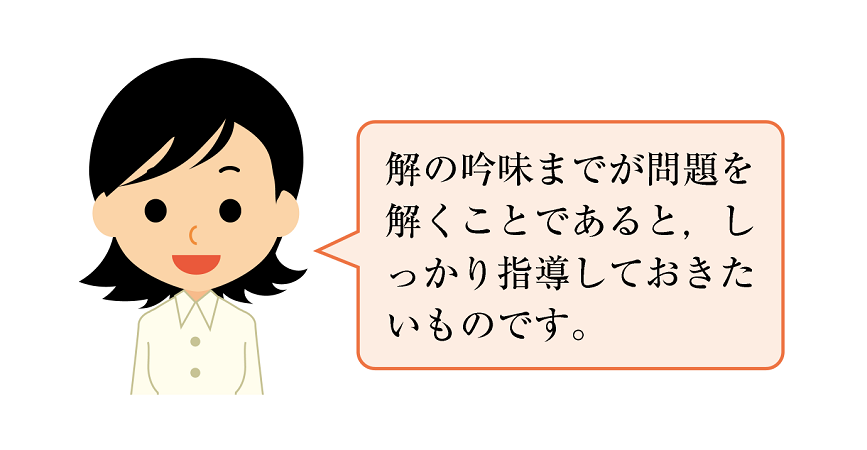
[3章]二次方程式
2節 二次方程式の利用(教科書p.81〜91)
アンケート
よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。
Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。

