今知りたい授業のワンポイント
空気中に出ていく水
■温度と水の蒸発
前単元では、水を熱すると100度で沸騰し、水が水蒸気となって空気中に出ていくことを学習しました。そのため、児童の多くは、蒸発するためには、加熱が必要であり、 100度にならないと蒸発が起きないと考える傾向にあります。
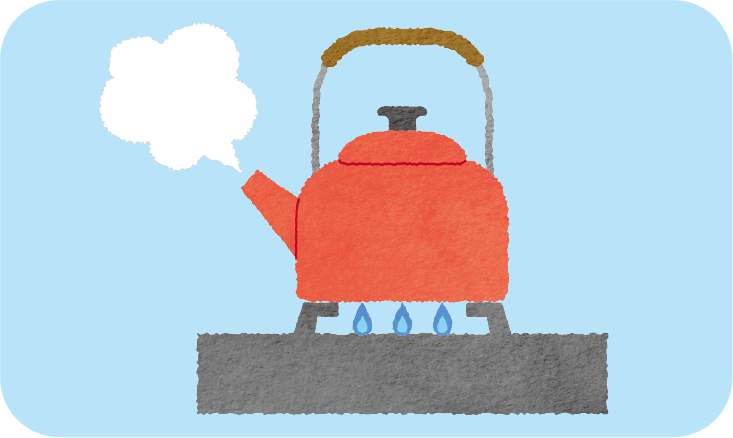
沸騰しているようす
100度より低い温度でも、水が蒸発するようすは、日常生活の中で数多く見られます。
・洗濯物の乾燥
洗濯物が乾くのは、洗濯物に含まれていた水分が蒸発し、空気中に出ていくからです。このことを理解させるには、洗濯直後の重さと、乾燥後の重さを比較することが考えられます。タオルなどの、水分を吸収しやすく乾きやすいものなどが最適です。
次に、洗濯物が乾く際に、洗濯物に含まれていた水はどこへ行ったのかを考えさせます。洗濯物を絞ったり、脱水したりしても完全に乾くわけではないことから、空気中へと出ていったことに気づくでしょう。また、そのときの温度は100度よりもずっと低いことから、沸騰しなくても水の蒸発は起こっていることに考えが及ぶように導きたいものです。
■実験のポイント
水を入れた容器を2〜3日の間、日なたに置いたときのようすから、水は熱しなくても蒸発して空気中に出ていくことを確かめます。2〜3日後に容器を確認するため、ほかの人が容器に触れたり、片づけられたりしないように配慮する必要があります。

■別の方法
日なたの湿った地面に、容器を逆さまにして置いておき、30分後に容器の内側のようすを観察します。地面が乾燥していると、地面からの水の蒸発が起こりにくいため、必ず湿った地面を選ぶようにしましょう。活動前に軽く水をまいておいても構いません。
日なたの湿った地面に容器を置く活動を行う場合には、容器が風で飛ばされないように、石などを乗せておきます。容器を置いた場所には、「実験中」であることが周りの人にわかるようにしておくとよいでしょう。

自然の中の水のゆくえ(2)11.水のゆくえ(教科書p.170〜179)
アンケート
よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。
Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。

