今知りたい授業のワンポイント
雨の日ならではの学校探検
■梅雨に対応した活動
梅雨に入り、雨の日が続いて室内遊びが続くと、子どもたちは外で遊びたくてうずうずするようになります。
そこで、小雨のときや雨上がりをねらって、雨の日にしかできない遊びを楽しんでみませんか。レインコートや長靴、タオルなど、準備をしっかり整えて外に出てみましょう。
雨の日の校庭では、雨の日特有の生き物を見つけたり、土のどろどろした感触を楽しんだり、水たまりにバシャバシャ入ったりすることができます。また、雨の日は影が見えないことやクモの巣や葉っぱについた水滴がきれいなこと、水たまりに自分の姿が映るなど、さまざまな「不思議」に出合うことができます。
子どもたちが、こうした気づきを1つでも多く体験できるよう、活動時間が十分確保できる計画を立てましょう。
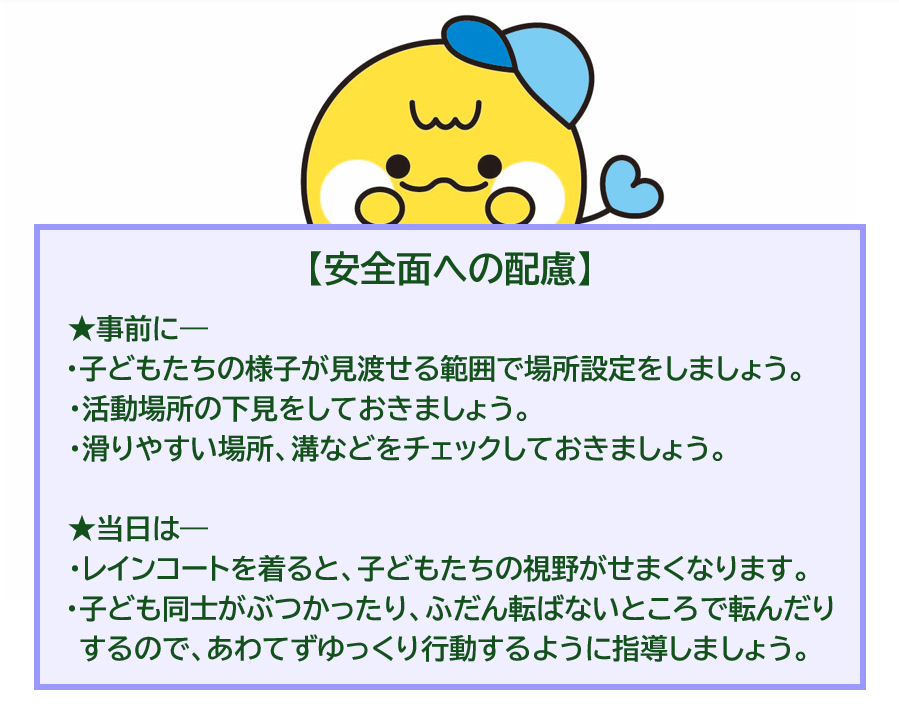
■動画「あめの ひの ふしぎ」
雨の日の活動を有意義なものにするには、ふだんから雨の日の様子を意識的に取り上げて話題にしたり、朝の会や帰りの会で紹介したりしながら、子どもたちの関心を高めておきましょう。
それには、教科書p.37のQRコードを使って、動画を見せるのが効果的です。
動画では、雨粒が葉から滑り落ちる瞬間や、さまざまな雨の音、雨の日特有の生き物(カエル、カタツムリ、アメンボ)の様子、クモの巣についた雨粒、レンズのようになっている雨粒など、雨の日ならではの様子や現象がたくさん盛り込まれています。子どもたちの好奇心をくすぐるものばかりなので、機会を設けて活用しましょう。
■音への気付き
ひと口に「雨」といっても、降り方や雨粒が当たる場所によってその音はまったく異なります。
例えば、激しく降るときは「ザーザー」、水面に雫が落ちる時は「ピチョン」、大粒の雨が傘に当たる音は「バラバラ」など、さまざまなオノマトペがあります。
子どもたちがその違いを楽しみながら、自身の感覚でどんな言葉で表現するか、耳を傾けてみましょう。

■熱中症の症状とその手当て
夏の野外活動において、最も注意しなければならないのは、熱中症です。
気温が高くなくても、暑くなり始めの梅雨明けの蒸し暑い日など、体が暑さに慣れていない時期は十分注意しましょう。
【症状】
①顔面が紅潮して、皮膚が熱くなる。
②体温(直腸温)が40度以上になったり、脈が速くなったりする。
③突然倒れて半昏睡状態になることもある。
【手当て】
①涼しい日陰で風通しのよい場所に寝かせる。
②衣服をゆるめて、楽にさせる。
③冷水をかけたり、アルコールに浸したガーゼを身体にはったりする。
④とにかく早く体温を下げる処置をして、医師を呼ぶ。
※意識(返事)がない、もうろうとしている場合は、ただちに救急車を呼びましょう。
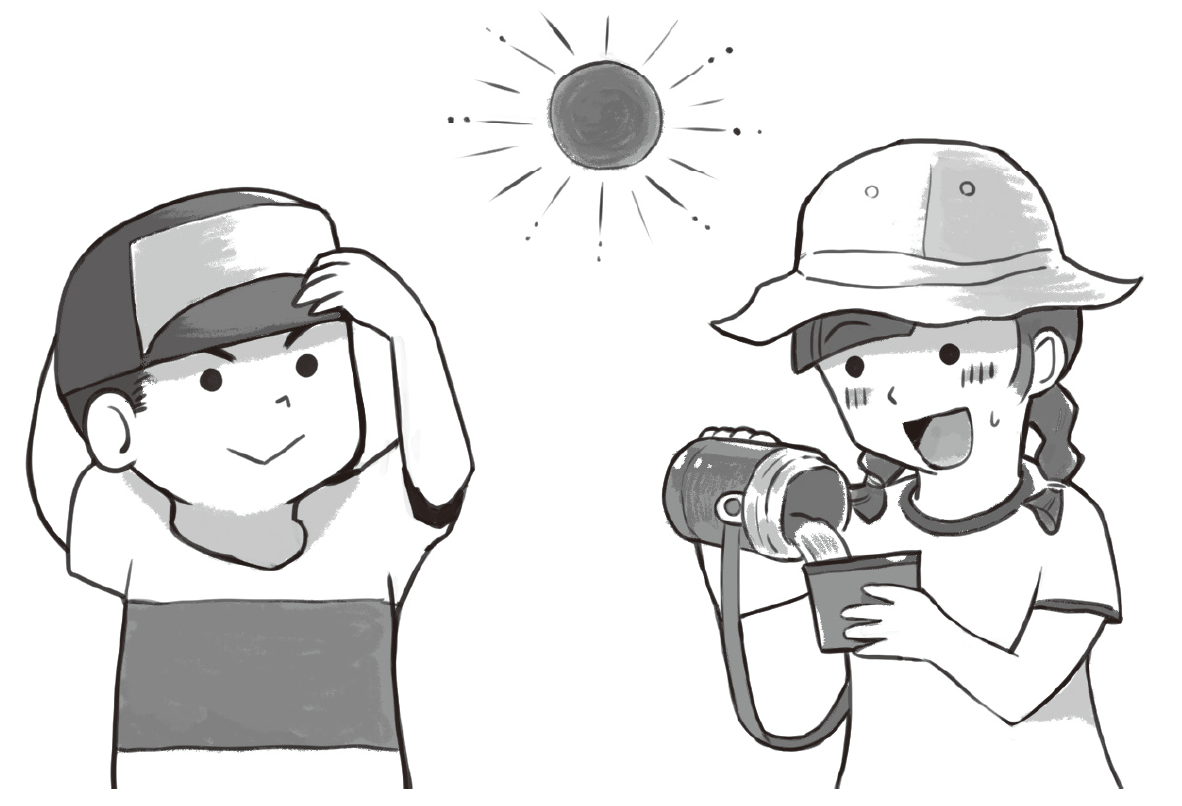
やって みよう(教科書p.36~37)
なつと なかよし(教科書p.38~41)
アンケート
よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。
Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。

